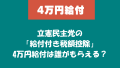2025年9月26、政府の地震調査委員会は南海トラフ巨大地震の発生確率を「80%程度」から「60~90%程度以上」へと変更しました。
この数字の変更に、「確率が下がったの?」と安堵した方や、「90%以上ってどういうこと?」と不安を増した方もいるかもしれません。
実は、この数字の変更の裏には、最新の科学的知見と、江戸時代の地震記録の再評価という重要な背景があります。
危険度が下がったと安易に考えるのは早計かもしれません。
この記事では、なぜ発生確率が変更されたのか、その具体的な理由を専門的な内容も踏まえつつ、誰にでも分かるように徹底解説します。
さらに、確率の数字に一喜一憂するのではなく、私たちが本当に知るべき防災のキーワードや、今すぐ取るべき具体的な行動についても掘り下げていきます。
数字の裏にある真実を正しく理解し、冷静な備えに繋げましょう。
- 確率変更はデータ精度向上が理由で、危険度が下がったわけではない。
- 「90%以上」という表現は、これまで以上に強い警告と受け止めるべき。
- 確率以上に重要なのが、前触れを知らせる「南海トラフ臨時情報」。
- 臨時情報には「警戒(事前避難)」と「注意(備えの再確認)」がある。
- ハザードマップ確認と備蓄品の見直しなど、具体的な行動が不可欠。
なぜ変わった?南海トラフ確率変更「60~90%程度以上」に
なぜ確率は「80%」から「60~90%以上」に変わったのか?
今回の確率変更の直接的な原因は、過去の地震データの見直しにあります。
特に、江戸時代に発生した「宝永地震(1707年)」と「安政東海地震・安政南海地震(1854年)」の地殻変動に関する記録(隆起量データ)に誤差があったことが判明し、より精度の高い計算をやり直した結果、確率が変更されました。
▼確率変更のポイント
危険度が下がったわけではない
「80%」という一つの数字から「60~90%」という幅のある表現に変わったのは、計算の精度が上がり、起こりうる可能性の幅がより正確に示された結果です。
「確率が下がった」と考えるのは早計です。
「以上」という言葉の重み
「90%程度以上」という表現は、計算上90%を超える可能性も否定できないという、極めて強い警告と受け取るべきです。
「いつ起きてもおかしくない」状況は変わらない!
結局のところ、地震調査委員会の平田直委員長が「これまで通り、南海トラフ巨大地震が発生する可能性は非常に高い」と述べている通り、私たちの危機意識や防災対策の必要性は何一つ変わっていません。
つまり、今回の改訂は「南海トラフ地震が遠のいた」という知らせではなく、「よりリアルな脅威の姿が見えてきた」という警鐘と取るべきです。
最重要キーワード「南海トラフ臨時情報」とは
地震の発生確率以上に、私たちの具体的な防災行動に直結するのが「南海トラフ臨時情報」です。
これは、南海トラフの震源域で「いつもと違う」現象が観測された際に気象庁が発表するもので、巨大地震の発生が通常時より高まっていることを知らせる重要なサインとなります。
この情報が発表された時、私たちはどう行動すればよいのでしょうか。
情報は観測された現象の切迫度に応じて、主に2つのキーワードで発表されます。それぞれの意味と取るべき行動を正しく理解しておくことが極めて重要です。
最も切迫度が高い情報:『南海トラフ臨時情報(巨大地震警戒)』
これは、巨大地震の発生が著しく高まったと評価された場合に発表される、最も警戒レベルの高い情報です。
発表されるケース
主に「半割れ(はんわれ)ケース」と呼ばれる状況がこれに該当します。
南海トラフの広大な想定震源域の半分(例えば、西側の九州・四国沖)で、先にマグニチュード8.0クラスの巨大地震が発生した場合、残りの半分(東側の東海・近畿沖)にも連動して巨大地震が発生する危険性が非常に高まります。
過去の宝永地震(1707年)や安政東海・南海地震(1854年)では、このように時間差で巨大地震が発生した可能性が指摘されています。
私たちが取るべき行動
この情報が発表された場合、政府は後発地震に備えて1週間の防災対応を呼びかけます。
特に、津波による甚大な被害が予想される沿岸部などで、自治体があらかじめ指定している「事前避難対象地域」の住民は、ただちに避難を開始する必要があります。
この地域は、「後発地震が起きてからでは津波からの避難が間に合わない可能性が高い」と判断されているエリアです。
事前避難対象地域でない場合も、外出を控えたり、すぐに避難できる準備を整えたりするなど、最大限の警戒が求められます。
ご自身の居住地や勤務地が事前避難対象地域に含まれるか、必ず自治体のハザードマップで確認しておきましょう。
注意を促す情報:『南海トラフ臨時情報(巨大地震注意)』
こちらは、「巨大地震警戒」には至らないものの、通常に比べて地震発生の可能性が高まっていると考えられる場合に発表されます。
発表されるケース
主に2つのケースがあります。
- 「一部割れケース」: 想定震源域の一部でマグニチュード7.0以上の地震が発生した場合。
- 「ゆっくりすべり」: 揺れを伴わずに、プレートの境界が数日から数週間にわたってゆっくりと滑る異常な現象が観測された場合。「ゆっくりすべり」自体は体に感じる揺れはありませんが、周辺のプレートにひずみを与え、巨大地震の引き金になる可能性が指摘されています。
私たちが取るべき行動
この情報が発表された場合、避難の呼びかけはありません。しかし、これは「安全」を意味するものではなく、「備えを再確認し、注意を怠らないでください」というメッセージです。
具体的には、以下のような行動を取りましょう。
- 防災リュックの中身を再点検し、いつでも持ち出せる場所に置く。
- 家具の固定や寝室の安全を改めて確認する。
- 家族との安否確認方法や避難場所について、もう一度話し合っておく。
- ハザードマップで自宅や職場、学校の津波や揺れの危険度を確認する。
実際に、2024年8月には日向灘でM7.1の地震が発生した際に、史上初めてこの「巨大地震注意」が発表されました。
これは、この情報システムが訓練や想定だけでなく、現実の脅威に対して運用されることを示す重要な事例となりました。
この「南海トラフ臨時情報」は、巨大地震という不確実な現象に対して、私たちが事前の心構えと準備をするための貴重な情報です。
キーワードの意味を正しく理解し、いざという時に冷静かつ迅速に行動できるように備えておくことが、何よりも大切です。
▼参考リンク
- 気象庁 | 南海トラフ地震に関連する情報
- 内閣府 | 南海トラフ地震対策
▼体験談から学ぶ「情報」の重要性
体験談から学ぶ「情報」の重要性:南海トラフ地震への備えを最新情報で強化する
東日本大震災を経験したAさんは、
「津波警報の後、ラジオで繰り返し『もっと高い場所へ』と呼びかけられているのを聞き、指定避難場所からさらに高台へ移動しました。
結果的に、最初にいた場所は津波にのまれてしまった。あの時、最新の情報を信じて行動したことが生死を分けたのです」と語っています。
この体験談は、災害時における最新かつ正確な情報がいかに重要であるかを物語っています。
そして今、私たちは南海トラフ巨大地震という、いつ起きてもおかしくない大規模災害に直面しています。
「30年以内に80%」から「60~90%以上」へ引き上げられた発生確率
政府の地震調査委員会は2025年9月26日、南海トラフ巨大地震が今後30年以内に発生する確率を、従来の「80%程度」から「60~90%程度以上」に見直しました。
これは、過去の地震に関するデータ分析の精度が向上したことによるもので、確率に幅を持たせたものの、依然として極めて高い発生確率であることに変わりはありません。
地震調査委員会の平田直委員長も「これまで通り、発生する可能性は非常に高い。防災対策を引き続き進めていただきたい」と警鐘を鳴らしています。
更新された被害想定:より甚大化する被害の現実
2025年3月には内閣府から新たな被害想定が公表され、被害の規模がより具体的かつ深刻であることが示されました。
- 激しい揺れと大津波:静岡県から宮崎県にかけての149市町村で震度7の揺れが発生する可能性があります。また、関東から九州にかけての太平洋沿岸の広い範囲で10mを超える大津波の襲来が想定されています。
- 増加する建物被害:最新の想定では、津波による全壊棟数は前回想定から22%増加し、18万8千棟にのぼると試算されています。
東日本大震災の教訓:「備え」がなければ情報は活かせない
Aさんのように情報を得て行動できた人がいる一方で、東日本大震災では多くの人が困難に直面しました。
- 安否確認の混乱:「家族の避難場所を確認するために、何カ所も体育館を回って探すのに苦労した」という声が多く聞かれました。
- 避難時の油断:毎年の避難訓練はしていても、「まさか本当に津波が来るとは思わず、身軽な格好で避難してしまった」という体験談もあります。
- 過酷な避難所生活:「アレルギー対応食がない」「プライバシーが全くない」など、避難所での生活は想像以上に厳しい現実があります。
これらの教訓は、正確な情報を得るだけでなく、その情報を活かすための事前の具体的な備えが不可欠であることを示しています。
私たちに与えられた「時間」:「南海トラフ地震臨時情報」
「南海トラフ地震臨時情報」は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、巨大地震発生の可能性が通常より高まった場合に気象庁から発表されます。
実際に2024年8月には日向灘で発生した地震に伴い「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されました。
この情報が発表されると、約1週間にわたり注意が呼びかけられます。
これは、私たちに避難や備えの最終確認をするための、いわば**「猶予期間」**が与えられることを意味します。この貴重な時間を無駄にしないために、今すぐ以下の行動を取りましょう。
- ハザードマップで自宅・職場のリスクを把握する
お住まいの地域が、津波による浸水、洪水、土砂災害などの危険性がある「事前避難対象地域」に含まれていないか、必ず確認してください。ハザードマップポータルサイトでは、様々な災害リスクを地図上で重ねて確認できます。 - 具体的な避難計画を家族で共有する
どこへ、どのルートで避難するのか。複数の避難場所と経路を確認しておきましょう。また、災害時に家族が離れ離れになった場合の連絡方法や集合場所を決めておくことが重要です。 - 1週間分の備蓄を準備する
食料や飲料水は最低3日分、可能であれば1週間分を備蓄しましょう。特に、携帯トイレ、モバイルバッテリー、常備薬は忘れずに準備してください。
災害は忘れた頃にやってきます。しかし、南海トラフ巨大地震はもはや「いつか来る」ではなく、「いつ来てもおかしくない」災害です。最新の情報を「自分ごと」として捉え、今日から具体的な備えを始めてください。
参考リンク
- 気象庁 :南海トラフ地震に関連する情報
南海トラフ臨時情報の詳細な解説や最新の観測状況が掲載されています。 - ハザードマップポータルサイト
ご自身の地域の浸水想定区域や土砂災害警戒区域など、災害リスクを地図上で重ねて確認できます。
最新の被害想定と「本当に役立つ」備え
確率論だけでなく、実際に起きた場合の被害を直視することも重要です。内閣府の最新の想定では、南海トラフ巨大地震による最悪の場合の被害は以下のようになっています。
死者数: 約23万1,000人(津波による死者が大半を占める)
全壊・焼失棟数: 約209万4,000棟
経済被害: 約171兆6,000億円(国の年間予算の1.5倍以上)
これらの数字はあくまで想定ですが、私たちが備えるべきことの大きさを物語っています。
熊本地震を経験したBさんの体験談が、備えのヒントになります。
「地震直後、電気・ガス・水道が全て止まりました。
一番困ったのはトイレです。幸い、キャンプ用の簡易トイレを物置に備蓄していたので本当に助かりました。
水や食料の備蓄はもちろんですが、衛生用品、特に携帯トイレは絶対に必要だと痛感しましたね。
あと、現金です。停電でカードも電子マネーも使えず、開いている店があっても現金がないと何も買えませんでした。」
▼今すぐ確認したい備蓄リスト
- 飲料水: 1人1日3リットルを目安に、最低3日分、できれば1週間分
- 食料: カセットコンロとボンベ、アルファ米、缶詰、レトルト食品など
- 簡易トイレ・衛生用品: トイレットペーパー、ティッシュ、ウェットティッシュ、生理用品など
- 情報・電源確保: 携帯ラジオ、モバイルバッテリー、乾電池
- 現金: 公衆電話用の10円玉も含め、ある程度の現金
- 常備薬・医療品: お薬手帳のコピーと共に、普段飲んでいる薬を1週間分以上
まとめ:なぜ変わった?南海トラフ確率変更「80%程度」から「60~90%程度以上」に
南海トラフ巨大地震の発生確率の変更は、研究が進展した証であり、私たちがより現実的な脅威としてこの地震に向き合うべき時が来たことを示しています。
「60%だからまだ大丈夫」「90%だからもう終わりだ」といった極端な解釈ではなく、「いつ来てもおかしくない」という冷静な認識のもと、今日できる備えを着実に進めることが最も重要です。
この記事を読み終えたら、ぜひご自身の、そしてご家族の防災対策を見直してみてください。
その小さな一歩が、あなたとあなたの大切な人の未来を守ることに繋がります。