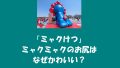自民党と公明党による長きにわたる連立政権は、日本の政治史において特筆すべき出来事の一つです。
しかし、2025年10月には、この連立解消のニュースが流れ、自民党と公明党の連立はいつから続いてきたのか、なぜ解散に至ったのかといった疑問を抱えている方が多いのではないでしょうか。
連立政権が始まったのは小渕恵三内閣のとき(1999年10月)であり、当初は「自自公連立」としてスタートしました。参議院での過半数割れという苦しい状況を打開し、重要法案を成立させるために組まれたこの枠組みは、その後の日本の政治に大きな影響を与えてきました。
この記事では、自公連立がいつから始まり、26年の歴史の中でどのような役割を果たしてきたのか、そして高市新総裁の登場や「政治とカネ」の問題といった背景のなかで、なぜ連立解消という大きな転換期を迎えることになったのかを、分かりやすく解説します。
この記事では、自民 公明 連立 いつから と検索した読者が、連立政権の始まりから解消に至るまでの経緯と、その政治的な背景について深く理解を深められます。
- 自公連立政権が発足した正確な時期と経緯
- 連立政権がいつから始まり、なぜ長期にわたって続いたのか
- 連立解消の直接的な原因となった自民党の「政治とカネ」の問題や政策的な対立
- 連立解消後の自民党と公明党の今後の関係
自民党と公明党の連立はいつから始まった?誕生の経緯
このセクションでは、自民党と公明党の連立政権がいつから始まり、どのような政治的な背景と経緯で成立したのかを解説します。
<目次>
連立政権が始まったのは小渕恵三内閣のとき

自民党と公明党の連立政権がスタートしたのは、1999年10月の小渕恵三第2次改造内閣の発足時です。このとき、自民党・自由党・公明党の3党連立政権として新たな枠組みが誕生しました。
連立政権の安定がもたらした成果
この連立政権によって、ガイドライン関連法や国旗・国歌法など、それまで長らく審議が難航していた重要法案が次々と成立しました。これは、当時の政権運営において連立が安定した基盤をもたらしたことの具体的な証左と言えます。
特に公明党は、小さな所帯でありながらも、この1999年10月から、民主党政権の時期を除き足かけ25年にわたり政権の一翼を担い続けてきた点で、日本の政治史において極めて特筆すべき存在であると考えられます。
きっかけは1998年参院選での自民党の大敗
自民党が連立政権を模索し始めた大きなきっかけは、その前年の1998年参議院選挙での大敗にあります。この選挙の結果、自民党は参議院において過半数を大きく割り込むこととなり、政権運営に深刻な支障をきたすようになりました。
野党の協力なくして法案成立は不可能に
参議院で過半数割れの状態に陥ったことで、予算案や重要法案の審議において、野党の協力なしには法案の成立が非常に困難になりました。
たとえば、参議院で予算案が否決されるなど、当時の自民党政権は重要法案の成立に不安を残した状態にあったと言えます。この政権運営の困難さを打開するため、自民党は他の政党との連携を急務としていました。
参議院での過半数割れで政権運営が困難に
前記の通り、1998年参議院選挙での大敗により、自民党は参議院で過半数を割るという厳しい状況に直面していました。
日本の政治制度では、衆議院で可決された法案も参議院で否決される可能性があるため、安定的な政権運営のためには参議院での与党側の過半数が不可欠です。
連立による安定多数の確保が目的
自民党は、公明党との連立を模索することで、参議院での安定多数を確保し、重要法案を円滑に成立させることを最大の目的としていました。
一方の公明党も、党の主張を政権運営に反映させるためには、政権に参加した方が得策であるという判断に傾き、連立参加を決めました。
この連立は、単なる数の論理だけでなく、公明党の掲げる政策を実現する上での実利的な側面も持っていたと言えます。
当初は自由党も加わった「自自公連立」としてスタート
1999年10月に発足した当初の連立政権は、自民党、自由党(当時の党首は小沢一郎氏)、そして公明党の3党によるもので、「自自公連立」と呼ばれました。
三党連立の短命と公明党の役割
しかし、この三党連立の枠組みは長くは続かず、後に自由党は連立を離脱します。
その後、自民党と公明党の二党連立へと移行し、この形が日本の政治において足かけ25年にわたる長期間続くことになりました。
この連立の成立は、イデオロギーや支持基盤が大きく異なる自民党と公明党が手を組むという、世界の政治学の常識を覆すものであり、日本の政治に安定をもたらす上で重要な役割を果たしてきたと言えるでしょう。
自民 公明 連立 の歴史に幕?2025年の最新動向

ここでは、自民 公明 連立 いつから続いてきた歴史が、なぜ2025年に終止符を打つことになったのか、その背景と今後の展望を解説します。
<目次>
- 公明党が連立離脱を表明、26年の歴史に幕
- 連立解消の最大の原因は「政治とカネ」の問題
- 高市新総裁との外国人政策や靖国参拝への懸念
- 25年間続いた連立期間中に公明党が果たした役割
- 「大衆の中に生きる」公明党のネットワークと機動力
- 連立解消後、予算案や重要法案では「部分協力」へ
- まとめ:自民 公明 連立 いつから 始まった?26年の歴史と今後
公明党が連立離脱を表明、26年の歴史に幕
2025年10月、自民党と公明党の連立政権は、26年という長きにわたる歴史に幕を下ろすことになりました。これは、先の衆議院選挙で与党が非常に厳しい結果となったことを厳粛に受け止めた公明党が、連立離脱の方針を固めたためです。
政権運営の継続は困難と判断
公明党の石井啓一代表は、自民党の石破茂総裁と会談し、連立政権の継続について協議を行いました。しかし、与党にとって厳しい選挙結果や、連立解消の最大の原因となった自民党の「政治とカネ」の問題を踏まえ、これまでの連立の枠組みを維持したままでは、国民の不信感を払拭し、政策実現に邁進することは困難であると判断したと考えられます。
連立解消の最大の原因は「政治とカネ」の問題
連立解消の直接的な最大の原因となったのは、自民党の派閥が引き起こした政治資金の不記載問題、いわゆる「政治とカネ」の問題です。公明党は、与党が選挙で大敗した大きな原因の一つに、この問題があるとして、自民党に「けじめ」を付けることを強く要求していました。
粘り強く「政治改革」をリード
公明党は、自民党が抵抗する中で、「政策活動費」の将来的な廃止を念頭に置いた政治改革ビジョンを掲げ、議論をリードしてきました。日本大学の西田亮介教授も、公明党が粘り強く現実的な落としどころを模索し、政治改革の役割を担ったと高く評価しています。
| 政策活動費改革に関する両党のスタンス | |
| 公明党 | 将来的な廃止も念頭に、廃止に向けて取り組むことを明確化し、政治改革を主導 |
| 自民党 | 抵抗する姿勢も見られたが、最終的に公明党の意向を概ね受け入れた |
このように、自民党が自浄作用を発揮できない中で、公明党が連立与党の自浄作用を担うという構図が見られたものの、信頼関係の根幹が揺らいだことが、連立解消という結果を招いたと言えるでしょう。
高市新総裁との外国人政策や靖国参拝への懸念
公明党が連立離脱を決断するまでの過程で、自民党の新しい総裁に就任した高市早苗氏の政治姿勢に対する警戒感も、懸念材料の一つとして浮上していました。
政策・理念の一致が不可欠
公明党の斉藤鉄夫代表は、高市氏の保守色の強い政治姿勢、特に靖国神社参拝や外国人政策の厳格化を主張する考え方について、懸念を伝えています。
斉藤代表は、会談で閣僚による靖国神社参拝が「これまで外交問題に発展しており、懸念を持っている」と指摘し、また「外国人を包摂し、一緒に社会を築いていくのは日本にとって必須だ」として、外国人政策に関する協議も求めました。
連立政権は政策と理念の一致が不可欠であり、この点で高市氏のスタンスが公明党の理念と完全に一致しない可能性があったことも、連立解消に傾いた一因と考えられます。
25年間続いた連立期間中に公明党が果たした役割
自公連立がいつから始まり、25年間という長期間にわたって続いた中で、公明党は「政権のブレーキ役・アクセル役」として極めて重要な役割を果たしてきました。
平和安全法制における「新3要件」
公明党の最も大きな役割の一つは、2014年の平和安全法制の議論において、当時の安倍首相が目指したフルスペックの集団的自衛権の行使に歯止めをかけたことです。公明党の緻密な理論武装により、集団的自衛権の行使を厳格に限定する「新3要件」が定められました。
- 日本国の主権が根底から覆されるような明白な危険がある場合に限定する(新3要件の1)
- 我が国の存立を全うし、国民を守るために他に手段がないという「自国の防衛」の措置としてのみ許される(新3要件の2)
- この「必要最小限度」を超える武力行使は、憲法改正なしには不可とする(新3要件の3)
これにより、公明党は平和の党としての理念を堅持しつつ、連立政権の枠内で政策の暴走を防ぐというブレーキ役の役割を見事に果たしました。
「大衆の中に生きる」公明党のネットワークと機動力
公明党が連立政権のパートナーとして自民党に選ばれ続けた背景には、その強固な組織力と現場を重視する姿勢があります。これは「大衆の中に生き、大衆の中で死んでいく」という精神性に基づいていると考えられます。
災害対策における存在価値
公明党の3000人近い地方議員と国会議員がフラットに連携するネットワークは、東日本大震災や熊本地震などの大規模災害において、被災者の小さな声を拾い上げ、政策に反映させる上で圧倒的な機動力を発揮しました。
- 復興庁の創設をはじめとする具体的な政策を野党の立場から矢継ぎ早に提起
- 被災各地の知事や市長らが公明党の機動力を高く評価
- 霞が関との意思疎通さえままならなかった民主党政権の対応とは対照的な役割
自民党の高石早苗新総裁も、公明党大会で「困っている人、悲しむ人たちのそばにいる自公政権でありたい」と挨拶したように、公明党の現場主義が自民党の政治姿勢に感化を与えた側面もあると考えられます。
連立解消後、予算案や重要法案では「部分協力」へ
自民党と公明党の連立政権は解消されましたが、両党の関係が完全に途絶えるわけではありません。特別国会に向けて、公明党と国民民主党は、案件ごとに政策協議を進めることで合意しており、今後の国会運営では部分的な協力が模索されることになります。
政策活動費の廃止に向けた継続的な取り組み
特に、政治改革においては、「政策活動費の将来的な廃止」を念頭に、引き続き取り組むことを合意文書で明確にしています。また、公明党の西田実仁幹事長は、国民民主党との会談で「年収の壁」の解消を具体的な政策協議の案件として提示するなど、国民生活に直結する政策での連携を求めています。
| 政策ごとの協力の可能性 | |
| 政治改革 | 「政策活動費」の廃止に向けた継続的な取り組みを予定 |
| 物価高対策 | 国民民主党との間で政策協議を進める方針 |
| 子育て・教育・若者支援 | 衆院選合意の内容を大筋踏襲し、政策ごとに連携を模索 |
連立解消はしたものの、政策ごとの是々非々の協力や、新たなパートナーシップの構築が、今後の国会運営の鍵を握ることになるでしょう。
まとめ:自民と公明の連立はいつから始まった?26年の歴史と今後
自民 公明 連立 いつから と検索した読者にとって、この連立政権が日本の政治に果たした役割と、その終焉が持つ意味は非常に大きいものです。1999年10月の小渕恵三内閣での発足から26年にわたり続いたこの枠組みの終焉は、日本政治の新たなフェーズを示唆しています。
- 自公連立政権は1999年10月に小渕恵三内閣で発足した
- 当初は参議院の過半数割れを解消するための「自自公連立」としてスタートした
- 公明党は民主党政権時代を除き足かけ25年にわたり政権を支えた
- 連立の長期継続はイデオロギーの異なる政党が組む「世界の政治学の常識を覆す」例だった
- 公明党は平和安全法制で「新3要件」を定め、政権のブレーキ役を果たした
- 災害対策などで「大衆の中に生きる」公明党のネットワークが機能し評価された
- 2025年10月に連立が解消された最大の原因は自民党の「政治とカネ」の問題である
- 高市新総裁の靖国参拝や外国人政策に対する公明党側の懸念も背景にあった
- 連立解消後も政策活動費の廃止など政治改革や重要政策で部分的な協力が模索される
- 26年続いた自公の連立解消は、今後の国会運営や選挙協力に大きな影響を与える
【参考】公明党の活動や政治改革に関する情報は、党の公式サイトや関連の出版物で確認できます。 >公明党 – 平和と福祉の党