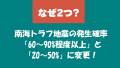「軽い気持ちで受けてしまったことを、少し後悔しています」
そう語るのは、今年(2025年)の国勢調査員を務めた70代の男性です。
5年に一度、日本に住むすべての人と世帯を対象に行われる国勢調査。
この国の未来を描くための大切な調査ですが、その最前線を担う「国勢調査員」の仕事は、私たちが想像する以上に過酷な現実があるようです。
「非常勤の国家公務員で、報酬も出るなら」と地域の依頼を引き受けたものの、待っていたのは想像を絶する労力と精神的な負担でした。
この記事では、70代男性のリアルな体験談を基に、国勢調査員の具体的な仕事内容、報酬、そして現場が抱える課題や葛藤を、最新の情報を交えながら徹底解説します。
「自分にもできるかな?」「報酬は割に合うの?」と考えている方、ぜひ最後までご覧ください。
国勢調査員はきつい?想像以上に大変!軽い気持ちで引き受け後悔!
【ターゲットキーワード】そもそも国勢調査員とは?
国勢調査員は、国勢調査の実施にあたり、総務大臣から任命される非常勤の国家公務員です。
地域の世帯を訪問し、調査票の配布や回収、問い合わせへの対応など、調査の最前線を担う重要な役割を果たします。
身分と任期
- 身分: 非常勤の国家公務員
- 任期: 調査期間中のおおむね2ヶ月程度
- 任命者: 総務大臣(市区町村からの推薦に基づく)
報酬の目安
報酬は担当する調査区の数(世帯数)によって変動しますが、一般的に1調査区(約50世帯)あたり5万円前後、2調査区(約100世帯)で7〜8万円程度が目安とされています。
年金暮らしの足しに、あるいは地域貢献のために引き受ける方が多いのが実情です。
体験談で知る!国勢調査員のリアルな仕事の流れ
ここからは、70代男性の体験談に沿って、調査員が実際にどのような仕事をしているのかを具体的に見ていきましょう。
ステップ1:準備段階(説明会、区域の確認)
最初に待っているのは、市区町村が開催する調査員説明会です。
「2時間ほど、映像を見たり資料の説明を受けたりしましたが、分厚いマニュアルを渡されて、正直気持ちが重くなりました」
説明会が終わると、次は担当区域の確認作業です。
地図を片手に、一軒一軒、実際に人が住んでいるか、空き家ではないかを確認して回ります。
「担当は約80戸。ただ歩くだけで1万歩を超えました。想像以上の体力勝負で、この時点で甘く見ていたことを痛感しましたね」
さらに、精神的な負担も大きいと言います。
「顔写真入りの調査員証を首から下げていても、住民からは訝しげな目で見られます。特に最近は防犯意識も高いですから、不審者と間違われないかヒヤヒヤしました」
ステップ2:地獄の仕分け作業と、仲間との絆
次に待っていたのが、各世帯に配布する調査票や説明資料の仕分け作業です。
「調査票、説明のチラシ、返信用封筒など、複数の書類を世帯番号に合わせて一部ずつ封筒に詰めていくんです。これが本当に大変で…。間違えたら大問題なので、何度も確認の連続。『最初からセットした状態で支給してくれればいいのに』と、つい愚痴がこぼれました」
しかし、この地域では指導員の計らいで、地域の集会所に調査員が集まって作業をすることができました。
これが大きな助けになったと男性は語ります。
「『あの家は外国の方だから英語の案内を入れよう』とか、『あそこは二世帯住宅だから2部いるね』とか、地域住民ならではの情報交換ができたんです」
作業の合間には、経験者から「夜に訪問したら逆に怪しまれて通報されそうになった」「配布が遅いと住民に怒鳴られた」といったリアルな苦労話も。
「一人でこの不安を抱え込んでいたら、きっと押しつぶされていました。仲間と顔を合わせて作業できたことが、何よりの心の支えでしたね」
ステップ3:配布開始!理想と現実のギャップ
9月20日、いよいよ調査票の配布が始まりました。
国の方針では「原則対面での手渡し」とされていますが、現代のライフスタイルとは大きなズレがありました。
「昼間は共働きで留守の家がほとんど。かといって、夜に訪ねるとかえって警戒されてしまう。インターフォンを押しても出ていただけないことも多く、結局、郵便受けに入れざるを得ないケースが多々ありました」
声をかけるタイミング、立ち去り方一つにも気を遣い、週末をかけてなんとか配布を終えましたが、「達成感よりも、どっと疲労感が押し寄せた」というのが本音でした。
ステップ4:最も過酷な「督促」と「聞き込み」
調査員の仕事は、配って終わりではありません。
インターネットや郵送で回答が提出されていない世帯には、繰り返し訪問して提出を促す「督促」が待っています。
「これが一番、精神的にこたえます。何度も伺うと『迷惑だと思われているんじゃないか』と、悪いことをしていないのに後ろめたい気持ちになるんです」
さらに、居住実態が不明な世帯については、近隣住民への「聞き込み」も行わなければなりません。
「『お隣にはどんな方が住んでいますか?』なんて、プライバシーに踏み込むようなことを聞くのは本当に気が重い。普段から人の出入りを監視しているわけでもないのに、どう尋ねればいいのか…」
この複雑な心境こそ、多くの調査員が抱える葛藤の正体です。
国勢調査員が直面する「5つの壁」
今回の体験談から、国勢調査員が直面する課題を5つのポイントに整理しました。
- 体力の壁: 担当区域を隈なく歩き回るため、想像以上に体力を消耗する。
- 精神的な壁: 不審者と見られる不安、住民からのクレーム、督促時の気まずさなど、精神的負担が大きい。
- 防犯の壁: オートロックマンションの増加で、玄関先にたどり着くことすら困難なケースが増えている。
- 制度の壁: 「原則対面」というルールと、共働き世帯や単身世帯が多い現代のライフスタイルとの間に大きなギャップがある。
- プライバシーの壁: 個人情報保護への意識の高まりから、住民が調査に非協力的であったり、聞き込み調査が困難を極めたりする。
現場からの悲痛な叫び「運用方法の改善を」
調査員をまとめる地域の町内会長のもとには、「インターフォンを押さないでほしい」という苦情と、「インターフォンを押して直接説明してほしい」という、全く逆の苦情が同時に寄せられたといいます。
板挟みになる現場の状況に、男性は強く訴えます。
「今の国勢調査のやり方には、正直無理があると感じます。もっと現場の実態に合った運用方法に見直してほしい。そうでなければ、なり手はいなくなってしまうでしょう」
一方で、「公募で選ばれた見ず知らずの人が地域を歩き回るのも、それはそれで不安だ」とも感じており、地域住民が担う意義も理解しているからこそ、気持ちは複雑に揺れています。
まとめ:国勢調査員はきつい?想像以上に大変!軽い気持ちで引き受け後悔!
国勢調査員の仕事は、報酬以上に大きな責任と労力が求められる、社会的に非常に意義のある役割です。
しかし、その運用方法は時代に合わなくなってきている部分もあり、現場の調査員に過度な負担がかかっているのが現実です。
この記事を読んで、もし調査員があなたの家を訪ねてきたら、ぜひ温かい対応を心がけていただけると幸いです。
そして、国には現場の声を真摯に受け止め、調査員も住民も、誰もが安心して協力できるような制度への改善を強く期待します。
私たちの国の未来を支える大切な調査だからこそ、そのあり方を社会全体で考えていく必要があります。
参考リンク
総務省統計局 令和7年国勢調査 特設サイト https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2025/index.html
国勢調査の目的や概要、最新情報が確認できます。
政府統計の総合窓口(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/
過去の国勢調査の結果など、様々な統計データが閲覧できます。