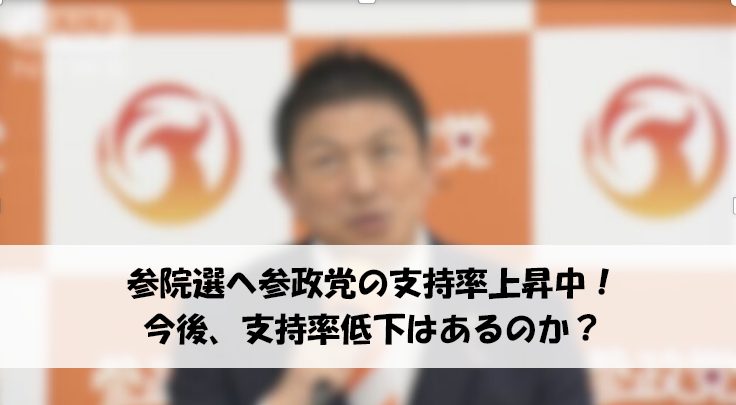参議院選挙が近づく中、注目を集めているのが参政党の支持率の上昇です。
SNSやインターネットを中心に若年層や無党派層からの支持を広げている参政党は、既存政党への不満の受け皿としても存在感を強めています。
しかし、急速な支持拡大の一方で、「なぜ支持率が急上昇しているのか」「今後もこの勢いが続くのか」「選挙後に支持率が下がる可能性はあるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、参政党の支持率が急上昇している背景や、今後考えられる支持率低下のリスク、そして今後の展望について、最新の世論調査や専門家の見解をもとにわかりやすく解説します。
参政党の動向が気になる方や、今後の日本の政治情勢に関心がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
参院選へ参政党の支持率急上昇!今後、支持率低下はあるのか?

参政党の支持率はなぜ上昇しているのか
2025年7月の参議院選挙直前、参政党の支持率は各種世論調査で4~9%台まで上昇し、野党の中でも上位に食い込む勢いを見せています。
この急伸の背景には、従来の政党とは異なる戦略や社会的な変化が複合的に作用しています。
1. 最新の支持率動向と具体的な数値
2025年7月上旬のNHK世論調査では、参政党の支持率は4.2%と報告されており、共同通信や日経新聞の調査では比例投票先として8.1%、政党支持率で9.2%と、野党内で3位~4位の水準に達しています。
都市部の選挙区や比例区での得票率予測は、上位シナリオで10%を超える可能性も指摘されています。
2. 若年層・都市部での支持拡大の具体例
世代別の分析では、参政党は30代以下の若年層で10%前後の支持を獲得しており、都市部では特にSNS世代の関心を集めています。
2025年6月の東京都議会議員選挙では、参政党が3議席を獲得し、都市部での存在感を示しました。
YouTubeやX(旧Twitter)でのライブ配信や「切り抜き動画」など、従来の政党が届かなかった層へのリーチに成功しています。
3. 既存政党への不信感・政治不満の受け皿
参政党の支持拡大は、単なる「保守層の受け皿」にとどまらず、政治への無関心層や従来の政党に不信感を持つ人々の新たな選択肢となっています。
2020年の結党からわずか5年で地方議員140人超を擁し、地方選でも着実に基盤を広げています。
「自民党では変わらない」「既存野党も頼りにならない」といった社会的な閉塞感や怒り、不信が、参政党の支持基盤を押し上げる要因となっています。
4. 政策・メッセージの明確さと独自性
「日本人ファースト」「消費税廃止」「子育て・教育給付金の拡充」など、具体的で分かりやすい政策を前面に打ち出しています。
企業・団体献金を受け取らない、という透明性の高さや、メンバーシップ制度による“DIY型ネット民主主義”など、他党と一線を画す運営方針も支持拡大の一因です。
政策決定に一般会員が参加できる仕組みが「自分たちで政党を育てる」感覚を生み、特に若年層や新規政治参加層に響いています。
5. 具体的な支持者層の特徴
支持者にはフリーランスや自営業、専業主婦、中年層の女性も多く、従来の「ネット保守」とは異なる多様な層が含まれています。
地方議員の増加や、地域課題に即した政策提案も地方での支持拡大に寄与しています。
このように、参政党の支持率上昇は、最新の数値や具体的な事例からも、社会の変化や有権者の新たなニーズに応える動きが背景にあることが分かります。今後の選挙戦でも、こうした独自のアプローチがどこまで広がるかが注目されます。
政策スローガン「日本人ファースト」の効果とは?
1. 街頭演説・公式発信での強調
参政党は2025年参院選において、「日本人ファースト」をキャッチコピーとして前面に掲げています。代表の神谷宗幣氏は公示日初日の演説で「積極的な財政政策や子育て支援、治安の確保を通じて日本人の生活を守る」と明言し、国民を中心に据えた政治を訴えています。
街頭演説やSNS、公式サイトでも「日本人ファースト参政党」と繰り返し発信し、党のアイデンティティや政策の根幹として強調しています。
2. 具体的な政策・公約への落とし込み
「日本人ファースト」は、消費税の段階的廃止、社会保険料の見直し、積極財政による手取り収入増、子育て・教育給付金拡充など、日本人の生活向上を直接目指す政策として具体化されています。
外国人政策では「無秩序な移民受け入れの見直し」「永住権・帰化要件の厳格化」「外国人による土地やインフラの買収制限」など、日本人の雇用や生活環境を優先する姿勢が明確に示されています。
3. 選挙戦略・候補者選定への影響
参政党は「日本人ファースト」の理念のもと、全国の選挙区で候補者を擁立し、地方議員の増加や都市部での議席獲得を目指しています。候補者選定や政策発信の際も、スローガンに沿った主張が重視されています。
「国民が主役」「自分たちで政党を育てる」というDIY型民主主義を掲げ、党員や支持者が政策立案や選挙活動に積極的に参加する仕組みも「日本人ファースト」の延長線上にあります。
4. 社会的議論・賛否の広がり
「日本人ファースト」スローガンは、既存政党への不満や社会的な閉塞感を背景に多くの支持を集める一方、排外主義や外国人差別につながるとの批判も強く、メディアや市民団体、専門家の間で議論が活発化しています。
実際の街頭演説やSNSで「日本人よりも外国人が優遇されている」といった訴えがなされることもあり、支持拡大と同時に社会的な波紋も広がっています。
5. まとめ
「日本人ファースト」という政策スローガンは、参政党の選挙活動や政策、公約、党運営のあらゆる場面で明確に反映されています。
その一方で、社会的な賛否や議論も巻き起こしており、今後の日本社会における大きな論点の一つとなっています。
参政党の支持拡大が顕著な地域・都市
1. 東京都(特に23区)
東京都議会議員選挙(2025年6月)で3議席獲得
世田谷区、練馬区、大田区の3選挙区で新人候補が当選し、参政党として初の都議会議席を獲得しました。
特に都市部の無党派層や若年層からの支持が強く、SNSを活用した情報発信が効果を上げています。
都内での得票率は7~10%台に達する選挙区もあり、都市部での浸透が顕著です。
2. 首都圏(東京・神奈川・埼玉)
東京選挙区
2025年参院選では、東京選挙区で1議席を争う展開も現実味を帯びており、都市部での組織化と無党派層の取り込みが進んでいます。
神奈川県
神奈川選挙区でも「保守層中心に支持拡大」と報じられ、都市部の有権者の間で存在感を高めています。
埼玉県
世論調査では埼玉選挙区でも一定の支持が見られ、都市近郊での拡大傾向がうかがえます。
3. 地方都市と地方圏
地方では都市部ほどの急伸は見られないものの、地方議員が150人を超えるなど着実に基盤を拡大しています。
地方都市や中核市でも、SNS世代や新規支持層を中心に徐々に浸透している状況です。
4. 支持拡大の特徴
都市部(東京・神奈川など)での得票率が高い一方、地方では3~6%程度にとどまる傾向があります。
30~40代のSNS世代を中心に、都市部での支持が特に強いことが最新の分析で示されています。
まとめ
参政党の支持拡大は、東京都を中心とする大都市圏で特に顕著です。都議選での複数当選や、東京・神奈川など首都圏での高い得票率が際立っており、今後も都市部を中心に党勢拡大が続く可能性があります。一方、地方では組織基盤の強化が課題ですが、着実に支持層を広げつつあります。
SNS戦略が中高年層にも影響を与えた具体例
参政党をはじめとする新興政党のSNS活用は、従来「若年層向け」とされてきましたが、実際には中高年層にも大きな影響を与えています。以下、その具体的な例やデータを紹介します。
1. SNS重視層の広がり
2025年の共同通信トレンド調査によると、参政党支持者のうちSNSや動画サイトからの情報を「重視する」と答えた割合は75.6%に達しました。特に40~50代の中年層でも44.2%がSNSを重視しており、参政党のSNS戦略が中高年層にも浸透していることが示されています。
他党(自民党、立憲民主党、共産党など)では中高年層のSNS重視率は2割程度にとどまるのに対し、参政党は突出した数値を記録しています。
2. 支持者層の実態
実際の支持者層についての調査・分析では、参政党の支持者は「若年層だけでなく、40代・50代の中年層や中年女性が多い」と指摘されています。YouTubeなどのSNSをきっかけに、これまで政治に無関心だった中高年層が新たに参政党を支持するケースが増加しています。
フリーランスや自営業、専業主婦など、従来の「ネット保守」とは異なる多様な中高年層がSNS経由で参政党の政策やメッセージに共感し、支持を表明する例が目立っています。
3. SNS活用の具体的な影響
参政党はYouTubeやX(旧Twitter)、TikTokなどで街頭演説や政策解説の動画を配信し、ライブ配信や「切り抜き動画」を通じて幅広い世代にリーチしています。
これにより、テレビや新聞を主な情報源としてきた中高年層もSNS経由で党の情報に触れる機会が増えました。
都市部だけでなく地方でも、SNSをきっかけに中高年層の支持が広がり、実際の選挙での得票や地方議員の増加に結びついています。
まとめ
SNS戦略は若年層だけでなく、中高年層にも確実に影響を与えています。特に参政党は、従来のメディアではリーチできなかった40~50代の中年層や主婦層、自営業層などをSNSを通じて新たな支持基盤として取り込むことに成功しています。
今後、参政党の支持率低下はあるのか

現時点では参政党の勢いが目立ちますが、今後の支持率については以下のようなポイントが注目されています。
支持率低下の可能性がある要因
1. 政策への賛否と批判の増加
2025年の参院選直前、参政党の政策や支持者に対する批判がSNSやメディアで急増しています。特に「カルト的」「極端」「知性の劣化」といったレッテル貼りや、国民主権や基本的人権を軽視した新憲法構想案への懸念が多く指摘されています。
代表的な例として、神谷宗幣代表の「高齢の女性は子どもを産めない」といった発言が物議を醸し、党の主張に対し一部メディアや有権者から「排外的」「過激」との批判が強まっています。
こうした批判が広がることで、特に都市部の無党派層や女性層の離反が懸念され、今後の支持率低下につながるリスクが懸念されています。
2. 組織基盤の弱さと地域格差
参政党は結党から5年で地方議員140人超を擁し、全国287支部を展開するなど急速に組織を拡大していますが、地方や高齢層への浸透は依然として限定的です。
特に鹿児島県など地方では、党員・サポーター数が約800人と、既存政党と比べて組織力が弱く、支部活動や資金面でも課題が残ります。
都市部ではSNSを活用した情報発信で若年層の支持を集める一方、地方や高齢層では「政党の実態が見えない」「評価は慎重にしたい」といった声も根強く、地域格差が支持率維持の障害となっています。
3. 他党の巻き返しと選挙戦略の変化
参政党の台頭を受け、自民党や立憲民主党など既存政党も政策や候補者戦略の見直しを進めています。たとえば、自民党は外国人政策や社会保障分野で参政党に近い主張を打ち出し、保守層や無党派層の引き戻しを図っています。
また、立憲民主党や共産党なども、参政党の一部主張に重なる政策を強調しつつ、選択的夫婦別姓や同性婚などで差別化を図る動きが見られます。
こうした他党の巻き返しによって、参政党への新規流入が鈍化し、既存支持層の流出が起きる可能性があります。
これらの要因が重なった場合、参政党の支持率は一時的な高まりから調整局面に入る可能性が高いと考えられます。特に、SNS上での批判拡大や地方組織の脆弱性、他党の戦略転換が今後の党勢に大きく影響すると思われます。
支持率維持・上昇の可能性
ネット戦略と若年層の取り込み
2025年の参院選直前、参政党の支持基盤は「ネット自盤」とも呼ばれるほど、YouTubeやX(旧Twitter)などのSNS活用が際立っています。最新の情勢分析によると、参政党支持者の約6割が「政治・社会情報の収集にYouTubeを長時間利用する」と回答しており、これは他党と比較して圧倒的な数値です。
若年層(18~39歳)では、既存政党への不信感が強まる中、参政党のSNS発信や動画コンテンツが「本音」や「現場感」を伝える手段として高く評価されています。特に30代男性の支持率は9.9%、18~29歳でも8.8%と、同世代の他党を上回る水準を記録しています。
参政党の公式YouTubeチャンネルでは、街頭演説や討論会のフル配信、切り抜き動画、政策解説など多様なコンテンツを展開。これにより、テレビや新聞に頼らない情報収集層への浸透が加速し、ネット世代以外にも中年層への波及効果が生まれています。
全国比例での候補者擁立
2025年参院選の比例代表名簿には、参政党から10名の候補者が登録されています。これは、同規模の中小政党と比較しても多い水準であり、全国規模での知名度向上と得票拡大を狙った戦略が鮮明です。
比例代表制の特性を活かし、地域や職業、世代を多様に反映した候補者を擁立。弁護士や医師、元スポーツ選手、現職議員など幅広い人材を前面に出すことで、従来の支持層に加え新たな有権者層へのアプローチを強化しています。
2022年の参院選では比例区で約177万票を獲得し、2025年はさらに得票拡大が見込まれる状況です。比例区での候補者数増加は、全国的な支持基盤の拡大と議席獲得の可能性を高める要因となっています。
まとめ
参政党は、SNSや動画配信を駆使した情報発信で若年層・ネット世代を中心に支持を広げると同時に、全国比例で多様な候補者を擁立することで、他の中小政党に対し優位性を確立しています。こうした戦略が今後の支持率維持・上昇のカギとなるでしょう。
参院選へ参政党の支持率急上昇!今後、支持率低下はあるのか?総まとめ
この記事では、参政党の支持率が上昇している背景や今後の動向について、最新の情報や専門家の見解をもとに詳しく解説しました。
参政党は若年層や無党派層を中心に支持を広げ、既存政党への不満の受け皿として注目を集めています。
しかし、急速な支持拡大の裏には、政策への賛否や組織基盤の課題、他党の巻き返しといったリスクも存在します。
今後、支持率が維持・上昇するか、あるいは低下に転じるかは、参政党自身の戦略や社会情勢、他党の動向など複数の要因によって左右されるでしょう。
今後の世論調査や選挙結果を注視しながら、参政党の動きや日本の政治の変化を見守ることが大切です。